❝ 今飲まれている焼酎は何年か前に造られたもの ❞
お酒好きの方ならここにロマンを感じるのではないでしょうか…。
多くの本格焼酎は熟成という時を経て世に排出されます。
今回は、本格焼酎を熟成させる理由と使用される熟成容器の種類についてお話します。
なぜ熟成させる必要があるのか。
熟成容器にはどんな種類があるのか。
この2点を解説します!!
1.本格焼酎を熟成させる理由
1-1 酒質の安定
蒸留したての焼酎には独特のガス臭が感じられます。
よく、新車のような匂いと表現されたりします。
一定期間貯蔵させることで、この不快に感じる匂い(ガス臭)を飛ばし、香りや風味を安定させることができるのです。
1-2 余剰な油性成分の分離
蒸留したての焼酎には油分が含まれています。
この油分は、空気に触れることで酸化をし、不快な油臭となります。
貯蔵させることで油膜を表面に浮かし、これを除去します。
この点に関しまして、以前詳しく解説したことがあります。
掘り下げたい方は「芋臭い焼酎という表現の撤廃 ~焼酎唎酒師の願い~」の芋焼酎の香りが向上した要因 ⑴ を参照ください。
1-3 水とアルコールの一体化
蒸留したての焼酎(約37~41度)には当然、アルコールと水が含まれています。
この2つの液体は、混ざり合っているようで分子レベルでは真に混ざり合ってはいません。
貯蔵という時間の力を借りることで、アルコールが水を包み込むような効果が出て酒質に円やかさを与えます。

以上3点が本格焼酎を熟成させる理由となります。
また、熟成期間に関しては各蔵元さん、各焼酎により異なります。
1年半~2年くらいの熟成が多いように見受けられます。
ちなみに、3年以上熟成させた焼酎を ❝ 長期熟成 ❞ とラベル表記することが認められています。
2.熟成容器の種類
2-1 タンク

大容量での貯蔵が可能であるというのが特徴です。
ステンレス製やホーロー製のタンクが使用され、容器の匂いが焼酎に移りにくいというメリットがあります。
デメリットとしては、他の容器に比べ熟成に時間がかかると言えます。
2-2 甕壺(かめつぼ)

甕壺は土に埋めて使用されることがほとんどです。
そのため、温度が低温で一定していることで外気の温度変化に強いと言えます。
また、素焼きの甕には細かい気孔(穴)があり、この気孔を空気が通ることで熟成を進め、焼酎の味わいをより円やかにさせます。
デメリットとしては、タンクに比べ大容量ではないと言えます。
2-3 樽(たる)

主にはウイスキー樽、シェリー樽が用いられます。
無色透明の焼酎にウイスキーのような琥珀色が付き、さらには樽の香りも移ることで個性的な風味になります。
しかし、酒税法では色度の制限を設けており、熟成期間には限りがあります。
(色が付き過ぎると焼酎とは名乗れなくなります)
そのため、長期の貯蔵を行うためには、他の容器と併用することになります。
また、あえて樽で長期熟成させ、しっかりと色付けして出荷している商品もあります。
この場合は焼酎とは謳えず、スピリッツと表記せざるを得ないことになります。
最後に
今回は、本格焼酎の熟成における基礎的なことを解説しました。
ここでひとつ言っておかなければならないことがあります。
それは、
❝ 熟成の長さは本格焼酎の良し悪しを図る絶対的なモノサシにはならない ❞
ということです。
ひとつの個性、特徴にとどまると認識しておくのがいいと思います。
原料の主張をはっきり表現させるため、あえて熟成を最小限にする焼酎もあります。
代表的なのは ❝ 新酒 ❞ です。
次回は ❝ 本格焼酎の日 ❞ に絡め、新酒についてお話します!!
今回も最後まで読んで頂いた方、ありがとうございました _(._.)_














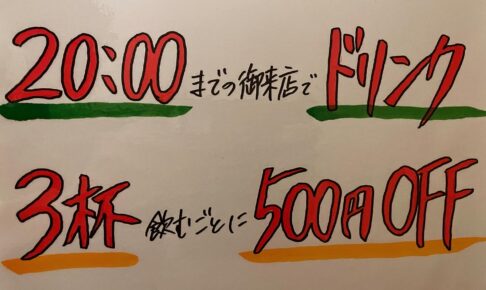



コメントを残す