僕が経営するお店「百伝」では ❝ 今月のおすすめ焼酎 ❞ と称し、
一ヶ月を通して一つの蔵元さんをピックアップする形を取っています。
10月は「八千代伝酒造さん」でした。
正直なところ、今月はこの蔵元さんのこと、お客さんにあまり話せませんでした。
飲まれた焼酎に対する反応は良かったのですが、
蔵元さんの話にまで発展がしなかったという点で僕の中では不完全燃焼でした。
これはひとえに僕の力不足であり、反省の一言であります。
ということで、今回のブログでは、
お店ではなかなか話すまでに至らなかった八千代伝酒造さんの歴史と
「百伝」という店名のきっかけとなったお話をさせて頂きます。
「行ってこい、八千代伝」との出逢い

八千代伝酒造さんの歴史についてはこの「行ってこい、八千代伝」という冊子に先代の社長の想いと共に深く刻まれています。
今から10数年前に僕は本格焼酎の造り手さんのことについて調べようと思いそれを行動に移しました。
きっかけは忘れましたが、八千代伝酒造さんのことから調べ始め、するとその歴史が書かれた冊子が存在することを知りました。
お付き合いのある酒屋さんに聞きましたが、わからないとのことだったので思い切って蔵元さんに電話をしました。
事情を説明するととても優しい口調で、
「興味を持ってくれたことが嬉しいです。すぐにお送りします」
と言ってくださいました。そして数日後「行ってこい、八千代伝」が届きました。
途中から号泣しながら読んでましたね。
僕は今まで何をしていたんだろう…。
僕が提供していた本格焼酎はやはりただの一杯ではなかった…。
そんなことを想い、自分が当時行っていた仕事の小ささと八千代伝酒造さんが一本の焼酎に掛ける想いとのギャップに呆然としてしまったのを覚えています。
「行ってこい、八千代伝」を要約すると、
先々代のときに閉めた蔵を先代が30年振りに再興するまでの軌跡が書かれています。
蔵に掛ける社長の想いとたくさんの方々の支えの下、再興させることができたということ。
そして再興して初めての焼酎(八千代伝)が出来、その初蔵出しを蔵人と支えてくれた人みんなで涙を流しながら見送ったという話。
この冊子が僕に与えてくれたものはとても大きく、
これを機に、他の蔵元さんについても精力的にアプローチをかけ、
そして多くの蔵元さんと出逢い、やがては今の自分を支えてくださる方々となっていきました。
百匹の猿

2010年、自身のお店を始めることになった僕はその店名を考えていました。
色々候補が上がりましたが、
初心に戻り、再び「行ってこい、八千代伝」を開いたとき、店名は決まりました。
「行ってこい、八千代伝」の一ページ目には ❝ 百匹の猿 ❞ というお話が書かれてあります。
要約すると、
九州のある猿島でのこと、一匹の猿が川に芋を落としそれを食べた。
うまいと思ったのかその瞬間から猿たちに芋洗いの習慣が根付いた。
子猿から親猿へと芋洗いの習慣が伝番していき、
そして100匹を超える猿がこの習慣を行うようになった頃、
なぜか遠く離れた東北の猿山で同じ習慣が根付いていった。
不思議としか言いようがない。
100という単位には何か大きな力があるのかもしれない。
という内容のお話です。
店名はこれだと思いました。
インターネットが当たり前のように普及していた2010年において、
この ❝ 百匹の猿 ❞ というお話の本質はただのおとぎ話ではないと思いました。
僕のお店から本格焼酎のこと、造り手さんのことを100人の方にきちんと発信することができたらこの世の中は変わる。
そんな風に考えました。
「百伝」という店名は八千代伝酒造さんの
❝「百匹の猿」の一匹にならん ❞
という想いに共感し命名しました。
これからも八千代伝酒造さんに恥じない仕事をしていきたいものです。
最後に

八千代伝酒造さんは今、業界も注目するお仕事に挑戦されています。
それは、原料となるさつま芋も自社栽培、
そして、麹米も自社栽培という徹底して自社栽培、自社製造にこだわっておられます。
現社長は僕と同い年です。
最近連絡を取っていませんが、こういう活動を耳にすると刺激を受けますね。
僕ももっと頑張ります!!
今月はもっとこういった話を店内でもしたかったんですけどね…。
ほんと反省してます。お客さんへのアプローチが弱かったですね…。
でもこの場では言いたいです。
八千代伝酒造さんは昔も今もスゴイ蔵元さんです。
僕が心から尊敬する蔵元さんです。
さて、来月は「国分酒造」さんをピックアップします。
ここの蔵元さんもアツいんですよ…。
ほんとは店内でお話できるのがいいんですけど、消化しきれなかった想いがありましたらこのブログでも発信していきます!!














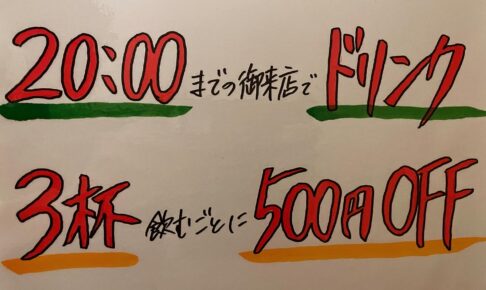



コメントを残す