本格焼酎のお湯割りは、どうすれば美味しく作れるのか?
これを僕の過去の経験と焼酎の造り手の方々とのお話の中で得たものを皆様にお伝えします!!
② 注ぐ順番は焼酎が先かお湯が先か
③ 適温は何度か
以上の順序に沿って説明していきます。
① 焼酎を割ることに対する皆様の考えと蔵元さんの考えにおけるギャップ
飲食店の現場で働いていた際、僕がお客様に何のアドバイスもせず、「お作り方はいかがしますか」と尋ねると大体の方は、「ロックで」とお答えしていました。
その理由を聞いてみると「人が造ったものを割るというのは失礼でしょ」というのが大半でした。
なるほど…。
では、
実際に焼酎を造っている方におすすめの飲み方を尋ねてみますと、その答えは、
「お湯割り」
というのがほとんどの蔵元さんの回答でした。
お湯割りで飲むことを想定して焼酎を造っているという蔵元さんもいるくらいです。
もちろん、ロックと答える蔵元さんがないわけではありません。
しかし、多くの蔵元さんがお湯割りをおすすめするのにはきちんとした理由があります。
その理由はいくつかありますが、ここでは3つ挙げておきます。
1.香り
当然の話ですが、空気(香り)は温度が低ければ下に行き、高ければ上に昇ります。
つまり、焼酎にお湯という熱を加え、香りを持ち上げているのです。
2.油分の融解
焼酎には目に見えない、いえ、時として目に見える油分が存在します。
これはもちろん、焼酎の原材料由来の良質な油分でして、本格焼酎における大事な旨味成分です。「高級脂肪酸エチルエステル」という成分で、焼酎の裏ラベルなどに「高級脂肪酸」や「エステル」などの記載がされていましたらその焼酎はお湯割りで頂くのがベストと言えます。
つまり、
この油分をお湯という熱で融解することにより旨味が広がるということになります。
3.食中酒という立ち位置からの提案
(これは水割りにも当てはまりますが)
焼酎はあくまでも食中酒であり、食事と共に楽しむものです。
もし、25度の焼酎をそのまま、もしくは氷のみを加えた場合、目の前にある料理の味を損なうことなく、味わうことができるでしょうか。
25度というアルコール度数が舌を覆い、本来の料理の味を軽減させてしまうとも考えられます。
飲む方の好みの濃さに合わせて、それを自由にコントロールできることも焼酎の楽しみの一つだと思います。
以上がお湯割りをおすすめする理由です。
もっとも、ロックを否定はしません。
多くの焼酎の中、この焼酎はロックだなというものが僕の中でもあります。
また、一年を通して現場で働いているといくら蔵元さんがお湯割りで!と言っても夏場にお湯割りをおすすめすることは僕にはできませんでした。
その季節、シチュエーションに応じたベストの飲み方というものがあると思います。
ですから、秋から春先くらいにかけては、焼酎本来の力を発揮する飲み方「お湯割り」を楽しんで頂きたいと思っています。

② 注ぐ順番は焼酎が先かお湯が先か
お湯割りを作る際、注ぐ順番として、
“ 焼酎が先か、お湯が先か ”という問題がよく議論されますね。
これに関して僕は、どちらが正解とは言い切れないと考えています。
とは言え、
僕が現場で働いていたとき、どちらの方法でお客様にご提供していたかと言うと、
「お湯を先に注ぎ、焼酎を後から注ぐ」
という方法を取っていました。
理由は二つです。
1.焼酎とお湯の比重の問題
焼酎の重さはお湯のそれと比べて重く、焼酎を後から注ぐことで対流が起こります。
つまり、自然と混ざり合うという利点があるのです。
2.割ったときの温度が全体的に均一になるから
サーモグラフィを使用した実験では、焼酎を先に注いだときと後から注いだときとでは、前者はグラスの上部の温度が高く、後者はグラス全体の温度がほぼ均一になります。
この二つの理由から、ステア(混ぜる行為)をしなくても提供できるという飲食店におけるオペレーション上においても大きな利点がありました。
これが僕が、
「お湯を先に注ぎ、焼酎を後から注ぐ」
手法を選んだ理由です。
では、もう一方が不正解とは言えない理由についてお話します。
それは、「焼酎を先に注ぎ、お湯を後から注ぐ」という作り方を文化としている地域があるからです。
鹿児島のとある漁師さん達の話です。
仕事が終わり、または、給料日になると楽しみの一つに焼酎がありました。焼酎が飲める!!ということに心躍らせていたのでしょう。
そんな気持ちから慌てて焼酎をグラスに注ぎ、後から追いかけるようにお湯を注いで飲む。
そういった習慣が根付き、その地域では、
“ 焼酎が先、お湯が後 ” という文化になったとされています。
僕が焼酎と出逢うずっと前から「これだよな焼酎は!」と言って、美味しく、楽しく飲まれている方々に対して、あなた方は間違ってると言えるでしょうか?
焼酎の造り手さんは口をそろえて言います。
楽しく飲んでもらいたいと。
正解があるとすれば、こういうことなんだと僕は思います。

③ 適温は何度か
先に言いますと、
42度~43度
を目指して作って頂きたいたいです。
問題は、
何度の焼酎と何度のお湯を合わせれば42度~43度になるのかということです。
ここでは焼酎とお湯の比率を3パターンに分けて説明します。
尚、焼酎の温度は常温とし、季節は先程提案しました秋から春先くらいを想定して記載します。
つまり、ここでは焼酎の温度を「15度~18度」とさせて頂きます。
お湯の温度は、「75度~78度」
⑵ 焼酎5 対 お湯5 の場合
お湯の温度は、「67度~72度」
⑶ 焼酎4 対 お湯6 の場合
お湯の温度は、「57度~62度」
今回は目安を示すため、焼酎の温度を「15度~18度」としましたが、冬場において実際の温度はもう少し低いです。
この場合は直接焼酎を温めるのではなく、暖かい部屋に少しの間置き、それからお湯割りにして頂くことをおすすめします。
または、グラスを一度お湯で軽くリンスし、グラスを温めるなどのひと手間を加えてみてください。
いくら焼酎の温度が低いからといってお湯の温度をこれ以上あげることはおすすめしません。
アルコール成分の揮発と香味成分が損なわれてしまうからです。


最後に
本格焼酎を飲むことで「脳梗塞」「心筋梗塞」の予防に繋がると言われています。
最近の研究結果では、(特に芋焼酎ですが)香りだけでもその効果が期待できるとされています。
本格焼酎をお湯割りにすることで原料の香りがより一層引き立ち、口当たりの円やかさ、甘さ、コク…
冷たい状態では感じられなかったその焼酎が本来持つポテンシャルが存分に発揮されます。
「お湯割り」は、心底おすすめできる本格焼酎の飲み方です。
P.S.
九州の方にお湯割りをお作りする際、これは僕の経験上ですが、ちょっとぬるかったかなと思うくらいでお出しすると意外に喜ばれるかもしれません。
コミュニケーションのツールとして是非、お試しください。
もし、ぬるいよと言われ、気まずい空気になりましたら、
ごめんなさい(笑)









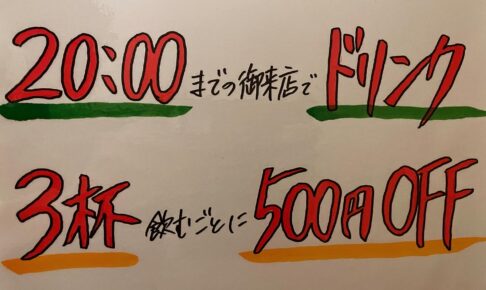



コメントを残す